不動産は所有権を登記できますが、複数人が所有者になる共有名義も許されています。
共有名義における名義人それぞれを共有者と呼ぶのですが、共有者の関係が良好であれば、共有名義はそれほど問題になりません。
問題が起こるのは、共有名義の不動産で何かしたくても、反対する共有者がいる場合です。結論から先に言ってしまうと、共有名義の不動産は、多くの場合に共有者の反対で身動きが取れなくなります。
詳しくは後で説明するとして、まずは不動産の共有名義がどのような状態なのか知っておくのと、これから共有名義にするかどうか検討している人は、慎重に判断して欲しいことだけは知っておいてください。
共有名義になる2つの代表的ケース
単独名義の所有者が、贈与等で近親者との共有名義になるケースを除くと、積極的に共有名義を望む人はそれほどいません。それは自分の所有物として自由にしたいからなのですが、どうしても共有名義を避けられないケースも出てきます。
その代表例が、夫婦や親子での連帯債務と、相続による不動産の取得です。
連帯債務(共同出資)による不動産の取得
不動産の購入資金が不足しており、借入金の審査で単独名義では借りられず、夫婦や親子の連帯債務として大きな金額を借りることは良くあります。借入金がないとしても、共同出資で不動産を購入することもあるでしょう。
このとき、購入資金の出資比率を持分割合とした共有名義にしなければ、出資比率よりも持分の多い側は、出資比率よりも持分の少ない側から贈与されたことになってしまうので要注意です。
共有者の関係悪化で面倒なことに
連帯債務による共有名義は、出資比率に合わせた権利を保全する当然の行為なのですが、不幸にも共有者の関係が悪化すると厄介です。
特に、親子と違って夫婦は離婚で他人になりますから、関係悪化後に共有名義になっているときは、不動産の取り扱いでもトラブルになりがちです。
相続による不動産の取得
不動産の所有者が亡くなって相続が開始されると、暫定的には相続人が法定相続分に従って不動産を共有しています。実際に共有名義とするかどうかは、遺産分割協議によって相続財産の分割が行われる過程で決まります。
つまり、暫定的な持分のある相続人同士が、不動産以外の相続財産と交換することで、共有状態は解消され、相続した不動産を単独名義にすることは可能です。
しかし、多くの一般家庭にとって、不動産(特に実家)だけが相続財産になることは少なくなく、不動産は物理的に分けることができません。
加えて相続人同士が争いを避けたい・決められないという事情もあり、法定相続分で共有名義にして登記するか、何も登記をしないで名義は故人のまま、相続人の共有状態が続いてしまうケースはとても多くあります。
相続による不動産の登記を相続登記と呼びますが、令和6年4月1日以降は、相続登記の申請が義務化されます。
相続が続くと共有者は増える
相続は主に高齢で行われることから、相続人も比較的高齢で、相続人が亡くなってさらに相続されることも十分考えられるでしょう。
相続人が亡くなると、その相続人まで共有名義の範囲が広がってしまい、共有者を把握するだけでも大変なのに、権利調整までするのは非常に困難です。
不動産の共有名義と共同使用・共同出資
不動産の共有名義を、共同使用する状態や、共同出資した状態と同様に考えているとハマります。共同出資を伴って共有名義になることがあるので、同じだと考えがちですが、全く違うことを理解しておかなくてはなりません。
共同使用の場合
私たちは普段から物を共同使用することが多くあります。公共物は言うまでもなく、私物でも親しい間柄でお互いに使うケース、一応は誰かの持ち物でも、事実上で一緒に使っているケースはいくらでもあるでしょう。
極端な例では、親の所有である家に子が住むのは、親が子に家を使わせていると考えることもできます。子は自分の所有物ではなくても「自分の家」と公言しますし、親もそのことをとやかく言いません。
しかしながら、これらのケースは誰かの所有物を他の人が使っているだけで、持ち主(所有者)は、自分の好きなように所有物を扱うことができます。
共同出資の場合
では、共同出資ならどうでしょう。例えば、仲の良い姉妹が、お互いにお金を出し合い、欲しいブランドバッグを購入して共同使用(共同所有)するとします。
姉も妹も同じ日にバッグを使いたいと譲らないとき、どちらが使うのでしょうか? 折半してお金を出したのなら同等だと言えますが、出した金額に偏りがあると、お金を多く出した側が優先権を主張すると考えられます。
これは、株式会社で保有株数に応じた議決権が与えられるのと同じです。多く株を所有しているほど議決権比率が高くなり、権利も大きくなって発言力が増します。
このように、共同出資では出資額割合に応じて権利の割合も変わるのが普通で、他の人よりも多く出資していれば、優先的に権利を主張できます。
共有名義の場合
不動産の共有名義では、不動産に変更を加える際、各共有者の同意を必要とします。不動産に変更を加えるとは、不動産が物理的に変化する土地の改良等の他、売却行為も該当しますので、共有名義の不動産は売却が不自由です。
もし、不動産全体を売りたいと共有者の誰かが思っても、共有者のひとりが同意しないだけで、不動産全体を売ることができません(全体で登記ができません)。
持分1/10と持分9/10の共有者がいるとき、1/10を持分とする共有者の反対に、9/10の共有者が持分の多さを主張しても通らないということです。
もちろん、共同出資で不動産を取得するときは、出資額に応じた持分割合の共有名義にします。だからといって、共有名義の不動産を売却するときは、出資額の多い(持分割合の大きい)共有者が優先されないのです。
各共有者が、自分の持分を売却するのは単独で可能ですが、共有者全員の同意がないと不動産全体を売却できないのが共有名義の特徴です。
一方、売却ではなく賃貸の場合には、不動産の「管理」とされ、過半数の持分で賃貸可能なケースもあるのですが少し複雑です。
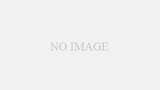
持分とは所有権の一部
共有名義の名義人であれば、所有権が持分で分けられていることくらいは知っているはずです。ところが、持分に対する誤解が多く、その中でも典型的なのが、不動産の一部分を持っていると考えてしまうことです。
持分とは所有権の一部であって、対象の不動産は共有者全員の共有物です。家屋は分けようもないですが、土地であっても持分に応じた面積で分けられているのではなく、全面積を全員で所有している状態です。
ややこしいことに、どの共有者も不動産全体について、持分に応じた使用をすることは可能です(民法第249条)。しかし、不動産は一体ですから、持分に応じた使用といっても、現実に一部使用は難しいものです。
そこで、誰かが自ら使用または第三者に使用させて得られた利益を、持分に応じて配分をすることで、共有者全員が持分に応じた使用を実現できます。
※持分については別記事で取り上げます。
持分の市場価値は低い
各共有者は、自己の持分を第三者に売却することが可能です。この点で各共有者は独立しており、他の共有者による同意を必要としません。
ところが、持分を購入しても不動産全体を自由に扱えないので、共有者以外の他人にとっては持分があってもそれほど意味がなく、必然的に持分の市場価値はとても低いです。
例えば、土地全体が1,000万円の価値、持分が1/2だとすると、持分を500万円で他人に売却するのは極めて難しく、本人は500万円分の資産を持っているつもりでも、実際にはとても500万円の資産とは言えないわけです。
したがって、持分の売買があるとすれば共有者同士(主に近親者)となって、このときは500万円の価値とみなして売買されるのかもしれません。
あるいは、購入する側が単独所有になるなら、土地全体を自由にできる付加価値が含まれることで、500万円以上での売買も考えられるます。
共有名義を解消する方法
必ずしも共有名義を解消しなければならないとは言えませんが、他の共有者から制限を受けるのが嫌になって、共有を解消したいとしましょう。
共有名義を解消する方法には、土地の分筆、持分移転、不動産全体の売却があり、これらのいずれかを裁判所に決めてもらう共有物分割請求訴訟も利用できます。
土地の分筆
共有不動産が土地の場合には、各共有者の持分に応じて分筆することで共有名義を解消できます。
分筆とは、ひとつの土地を複数に分けることで、分筆後の土地にはそれぞれ所有権を登記できるため、分筆後の土地を共有者それぞれの単独名義とするのです。
分筆で気を付けるとしたら、分筆後の面積ではなく「分筆後の評価額」が持分割合に概ね一致しないと、正しい分け方にならない点です。
どのように分筆しても、接する道路、形状などの違いで、分筆後の土地の評価は変わりますから、持分割合を維持できる評価額に分けなくてはなりません。
また、一般に分筆した土地の合計評価額は、分筆前の土地よりも低くなるので、その点も考慮して分筆を考えるべきです。
持分移転
共有者が他の共有者に持分を移転する方法で、一般には売買か贈与によって行われます。全ての持分を一人の共有者に移転すれば単独名義になります。
もっとも、単独名義を希望している共有者がいなければ実現せず、売買で持分移転する場合には、代金を支払えるだけの資力も必要です。
連帯債務のときは金融機関の同意も必要
連帯債務による共有名義では、単独名義への変更に対して、金融機関の同意を必要とするのが一般的です(ローン契約に定められています)。
より正確に言うなら、単独名義への持分移転は可能ですが、金融機関の同意を得ずに持分移転をすると、契約違反で一括返済を求められる可能性があるということです。
単独名義にした結果、持分を移転した側は所有者でもないのにローンを組んでいることになり、この状況はローン契約時の想定外であるため、金融機関の同意を必要とすることが多いのです(金融機関が同意するかどうかは別問題です)。
不動産全体を売却
不動産全体を第三者に売却して、その売却代金を各共有者の持分割合に応じて分けます。
当然ながら、不動産全体の売却では他の共有者に同意が必要で、共有者全員が売主となって売却します。共有者全員が売却手続に参加できなくても、委任状で手続を代理してもらえば、誰かが代表して売却することは可能です。
※共有名義での売却は別記事で取り上げます。
相続登記前なら便宜的な単独名義が許される
登記された共有名義では、共有者全員が売主にならないと売却できませんが、相続での暫定的な共有で登記前なら、代表者の単独名義で登記して、代表名義人が単独の売主になることもできます。
この場合でも、相続人全員の同意が必要なのは変わらず、売却代金を分配する目的で代表名義人に持分を集めても、便宜上の行為として贈与に該当しないとされています。
共有物分割請求訴訟
贈与・売買による共有者間の持分移転、共有者全員による不動産全体の売却、土地の分筆による共有解消は、当事者の合意によって行われるため、反対する共有者がいるとできませんよね。
しかし、各共有者は共有解消を目的にいつでも共有物の分割を請求できることが、民法で認められています。したがって、他の共有者が反対するかどうかは関係ありません。
民法 第二百五十六条第一項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
e-Gov 民法
他の共有者が反対するときは、他の共有者全員を相手に共有物分割訴訟を提起することにより、共有解消のための分割方法が裁判所から命じられます。
具体的な分割方法としては、現物分割、代償分割、換価分割となりますが、これまで説明してきた共有の解消方法と基本的に同じです。
| 現物分割 | 建物を現実に分割することは難しいため、主に土地の分筆で共有を解消します。 |
| 代償分割 | 共有者の一人に他の共有者の持分を買い取らせることで共有を解消します。 |
| 換価分割 | 競売により売却した代金を各共有者に分配することで共有を解消します。 |
共有物分割請求は、民法で認められた請求権ですから、権利濫用に該当する事情がなければ、裁判所は分割請求を認める傾向ですが、訴えた共有者が希望する分割方法になるとは限りません。
共有名義から抜けたいなら持分売却か持分放棄
単に自分だけが共有名義から抜けたい場合、その方法は持分売却と持分放棄の2つです。
持分売却
他の共有者へ持分を売却するのは、結局のところ持分移転による共有解消と変わりませんので、ここで説明する持分売却は、共有者以外の第三者への売却です。
不動産全体の売却と異なり、各共有者が自分の持分を売却するのに他の共有者の同意は必要ありません。つまり、各共有者は自分の持分を自由に売却できます。
この点が、持分売却における最大のメリットで、前述したように、持分の市場価値は現実の評価額よりも低く、持分を現金化しても、不動産全体を売却して代金を分配するよりも安くなります。
売却価格が安くなってでも持分を手放したい、もう共有名義には関わりたくないという共有者は、持分売却も考えてみるべきでしょう。
持分売却を専門に扱う不動産会社がある
不動産会社は無数に存在しますが、持分売却を扱う不動産会社は少ないです。その理由は、持分売却が潜在的に他の共有者とのトラブルを含んでおり、はっきり言って「難しい」「やりたくない」からです。
また、法的な知識や不動産売買の経験がある不動産の共有者は少なく、自分ひとりでは何をしたら良いのかわからないというのも実情でしょう。
持分売却のようにニッチな分野は、一般の不動産会社よりも専門の不動産会社に頼ったほうが成功率は間違いなく上がります。元から売るのは難しい持分なので、売れたらラッキーくらいに考えてダメ元で相談してみてください。
持分放棄
持分放棄とは、共有者が自分の持分を放棄することで、他の共有者へ帰属させる方法です。放棄された持分は、他の共有者が持分割合に応じて取得します。
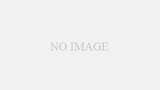
一見すると便利な持分放棄ですが、放棄された持分は他の共有者への「みなし贈与」と扱われ、贈与税が課せられますので注意が必要です(相続税法第9条)。
また、そもそも持分を欲しい共有者がいるなら、その共有者と売買・贈与すれば済むわけですから、持分を放棄するとしたら、誰も持分を欲しがらない場合が多いと思われます。
そうすると、持分を放棄した人は共有関係から抜けてスッキリしますが、放棄された持分を強制的に引き受けるしかない他の共有者は、望まない持分を引き受けて、さらに贈与税まで支払わなくてはならずトラブルを起こしやすいでしょう。
まとめ
共有名義の問題点は、様々な場面で共有者の同意を必要とする不自由に尽きますが、共有者の意思が一致しない=トラブルを起こすということです。
トラブル含みの不動産は誰でも嫌いますから、持分を売ってしまおうと思っていても、説明したとおり持分の市場価値は高くありません。
ですから、共有者と意思の疎通が図れる状態のうちに、不動産をどうするべきか話し合って、共有名義を解消できるようにしておくべきでしょう。
ただし、出資比率や相続分に応じた持分で共有名義にすることは、むしろ正常であって、メリットになるかデメリットになるかは、共有者の関係性しだいです。
将来も踏まえた上で協議して共有名義にするのであれば問題ないのですが、共有名義にした当事者と、その相続人で意見が一致しているとも限らないので、相続のタイミングで共有名義を見直すことも必要なのではないでしょうか。

